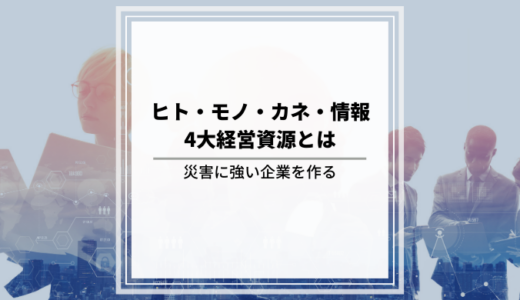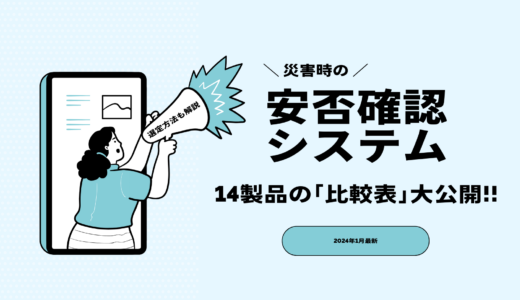大災害など緊急事態が生じた場面、地域が頼りとする業種のひとつ、それが建設会社です。そのため、他業種以上に、事業継続計画(BCP)が重要になってきます。
ただし、単にBCPを策定すればいいというわけではありません。建設業でのBCP策定においては、インフラを支える業種ならではの特質を考慮したうえで、BCPを策定する必要があるのです。
そこで今回は、全国建設業協会や日本建設業連合会の資料を参考に、建設業のBCP策定におけるポイントをわかりやすくまとめました。まず建設業がBCPを策定する重要性を説明し、次いで担当者が容易にBCPを策定できるよう、流れと注意点について建設業の視点から解説します。
建設業のBCP担当者は、ぜひ参考にしてください。
なぜ建設業にとってBCPが重要なのか

まず建設業にとってBCPがなぜ重要なのか説明する前に、先の東日本大震災で建設会社がどのような機能を果たしたのか記さなければなりません。
日本建設業連合会の発表によると、未曾有の被害を出したこの災害において、多くの建設会社が復興(防波堤、防潮堤・橋など)、機能回復(浄化センター・水路など)、除染活動などに協力して地域に貢献したと言われています。
このような対応をするためにも建設業の企業は、「行政と協働していち早く現場に駆けつけ、迅速に応急復旧を行うこと」や、「ライフラインの復旧を通じ、住民生活の救援にあたること」が災害時の役割として求められています。そしてその役割を果たすためには、企業自らが事業活動を継続できる体制を整えなていなければなりません。
さらに、社会全体の早期復興に直結する、迅速なインフラ復旧工事は、建設会社のCSR活動のひとつとして位置づけられています。つまり企業のBCP担当者は、BCP策定が自社だけでなく社会全体の利益につながっているという意識を持つべきなのです。
BCP策定における簡単な流れ

建設業におけるBCP策定方法(平成27年度の内閣府調査参照)については、「国や地方公共団体が公表している文書等を参考とした」が67%、「業界団体のガイドラインを参考とした」が46%となっています。これをふまえ、この章では日本建設業連合会が平成24年11月に公表した「建設BCPガイドライン」に沿って、具体的なBCP策定のプロセスを追っていきましょう。
(1)検討対象とする災害の特定
まずは、BCPを策定するには、検討する対象として、事業に著しいダメージを与えかねない重大災害を想定しなければなりません。例えば、自然災害に加え、新型インフルエンザ、犯罪・事故、環境汚染など……。それぞれの災害に応じて、BCPも異なります。
このステップでは、政府や各都道府県のHPなどで震度分布図やハザードマップなどを参考にするとよいでしょう。
(2)影響度の評価
災害によって会社にどの程度の影響が出るのか測定するのが、影響度の評価のステップです。
①停止期間と対応力の見積もり
重要な業務について、さまざまな観点から、企業としてどの程度まで耐えられるか(操業度の下限と、復旧時間)の分析と判断を行います。
②重要業務の決定
被災後、すべての事業・業務を早急に実現することは困難です。活用できる人、物、経営資金等には限界があることを想定して、継続すべき重要業務を絞り込みます。応急復旧工事が求められる災害(地震など)と、必要とされない災害(新型インフルエンザなど)とに分けて考えるとよいでしょう。
③目標時間の設定
上記した重要業務の再開までにかかってよい(許される)時間を、業務ごとに策定します。この目標時間は、取引先などに対して、よほどのことがない限り実行するという公約になることを留意しましょう。
(3)重要業務が受ける被害の想定
事務所・工場、機材、要員、原料、輸送など、さまざまな経営資源が受ける被害を考慮し、被害を想定します。
(4)重要な要素の抽出
重要業務の継続に不可欠であるものの、再調達や復旧に手間がかかりかねない重要な要素(ボトルネック)を洗い出します。BCPの策定においては、このボトルネックを乗り越えるための戦略を立て、対策を講じなければなりません。
(5)BCPの策定
上記をふまえて、具体的なBCPを策定します。この際、中小企業庁が公表しているテンプレートは、BCP作成の所要時間によって入門・基本・中級・上級の4コースに分かれており、利便性についても信頼性においても高評価を得ているため、ぜひ活用しましょう。
建設業だからこそとくに注意すべきポイント

数ある業種の中で、街を支える建設業だからこそ注意すべきポイントがあります。それは、BCPの本来の目的である「“平常時の”業務の継続または早期に復旧」だけではなく、インフラ復旧工事など、むしろ「“災害後に新たに発生する”業務への対応」までしなければいけない、という点です。
そのため、建設会社のBCP策定においては、「通常業務の継続」と「応急業務への対応」に分類して考える必要があります。
その応急的に求められる対応は、具体的には以下のようなものが挙げられます。
(1)インフラ復旧工事への迅速な対応
建設業は、地震など広域自然災害で復旧活動の中心となります。そのため、事業継続や早期の事業再開が、水道やガスなどのライフライン企業と同様に迅速でなければなりません。
また、道路等の復旧は、自社のほかの重要業務(施工中現場や竣工物件への対応)の早期復旧や稼働にも大きく関わってきます。
特に災害協定や施設管理契約を締結している企業は、自社の分担部分の業務を早期に対応する必要があります。さらに、もし被害が甚大で工事を再開できない場合、他企業に早い段階で出動要請しなければなりません。
(2)竣工物件への対応
竣工物件への対応も、建設業ならではです。
ご存知のことと思いますが、建設業者は工事引き渡し後も一定期間は責任が継続します。
そのため、施工した物件への責務と施主との信頼関係保持のために、自社施工物件の状況確認と施主へのフォローをしなければなりません。とくに災害発生直後は対応できる人的資源に限りがあることから、優先順位をあらかじめ決定しておく必要があります。
(3)施工中物件への対応
建設会社において、施工中の物件の品質を管理することと工期を遵守することはビジネスの核の部分です。そのため、もし被災した場合でも迅速な工事再開が望まれます。
大規模地震など、被災が不可抗力による場合は、工事の一時中断・工期の延長が許されるケースが多いですが(不可抗力条項)、現場周辺の二次災害を防止するという社会的責任の観点からも、災害の発生後、できるだけ早く施工中の現場の被害状況を確認することが望まれます。
(4)協力会社との連携
建設会社は一般的にピラミッド型組織であり、事業拠点が多数あることでしょう。そのため、拠点ごとに協力会社を事前に把握しておき、非常時にも確実に連絡がつく手段を確認しておくことが重要です。また一方で、被害の少ない協力会社を確保することができれば、災害時にも多数動員が可能といったメリットもあります。
まとめ
ここまで建設会社の特徴とそれがBCPに及ぼす影響を挙げてきましたが、ほかにも、「防災・減災技術を保有しており、建物や敷地の危険度判定ができる」「現場が平時より地域と密着しているため、災害時には周辺地域の救助活動に協力できる」「屋外作業が多いため、本社が被害を受けても、人員や情報を確保できれば事業継続できる可能性が比較的高い」など、他業種にない要素が建設会社にはあります。
そしてこれらの特性があるからこそ、災害時には建設会社がインフラ復旧や支障物撤去等の重要な担い手になるのです。社会的にも求められている建設業におけるBCP策定。この記事が策定の助けとなることを期待しています。
<参考文献>
「事業継続マネジメントとBCPがよくわかる本」(打川和男著、秀和システム)
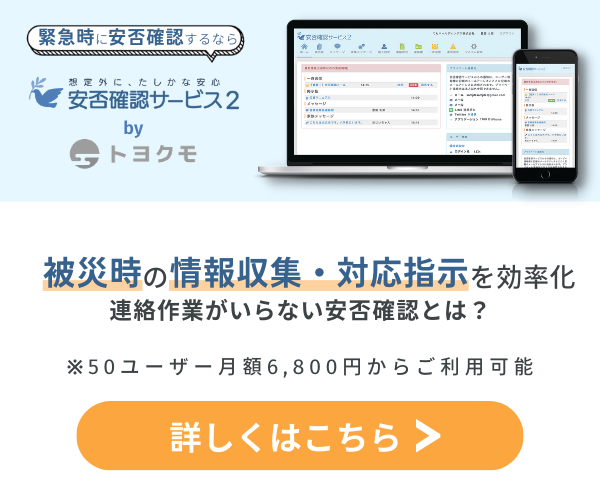
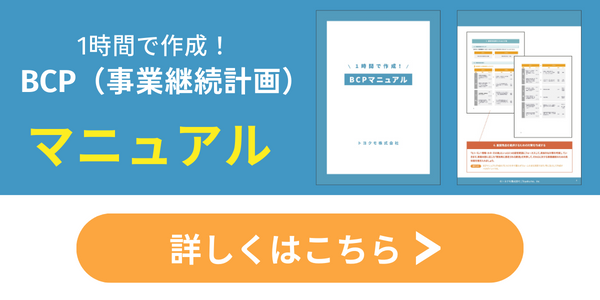
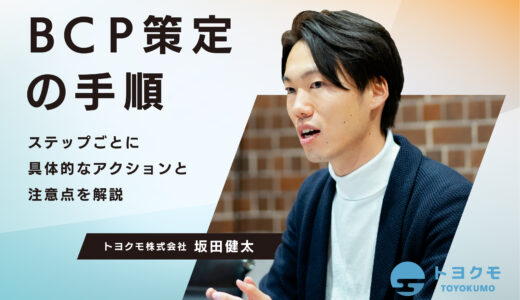
を1時間で作る!-520x300.png)