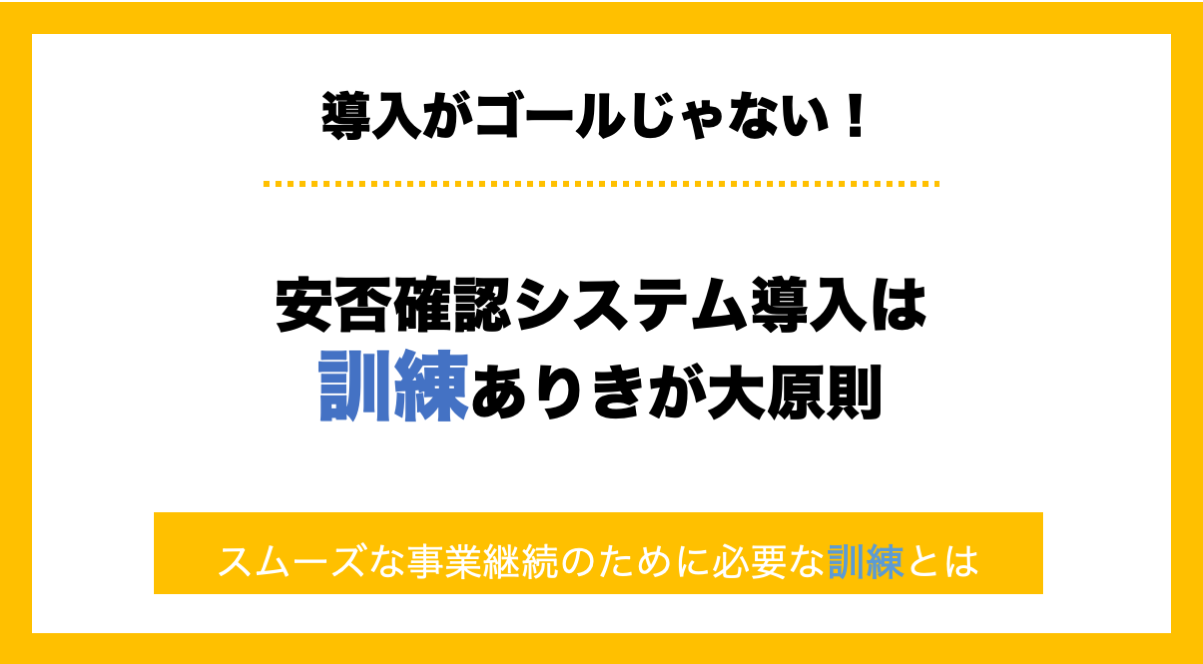大きな地震・台風などの災害は珍しくなくなり、たびたび死傷者が出るほどの事例が起こっています。何としても被害を抑えたいところですが、自然災害の発生そのものは防げないため、私たちは限られた範囲で対策を講じなければなりません。
そこで今回は、一般住民や自治体職員がグループで取り組める、さまざまな防災訓練をご紹介します。
企業向けの防災訓練はコチラ!
 全編アーカイブ配信!感染症BCP対策の大枠を捉えるセミナー
全編アーカイブ配信!感染症BCP対策の大枠を捉えるセミナー 目次
防災訓練とは
防災訓練は、災害時に適切な行動ができるよう、災害を想定して行う事前訓練のことです。たとえば、私たちは地震が起こった際に頭を守ったり、脱出口であるドアを開いておいたり、災害時に最低限の対処をスムーズに行えるのはどうしてでしょうか?
多くの場合は、小中学生のときに何度も防災訓練を経験するなかで、教師や消防隊員などから対処法を指導されたからです。このように、防災訓練には「パニック時に冷静な対処ができる」という、命を守るうえで重要な判断力を身に付けさせる効果があります。
人命を守るという重要な役割を持った防災訓練を、本記事では以下の2つに大別して解説していきます。
| 防災訓練の種類 | |
|---|---|
| 一般住民向けの防災訓練 | 災害時に迅速かつ適切に行動するための訓練 |
| 自治体職員向けの防災訓練 | 自治体の住民たちを災害から守るための訓練 |
それぞれ、どのような内容の防災訓練を行うのか、細かく分類しつつ確認していきましょう。
一般住民向けの防災訓練

一般住民向けの防災訓練には、どのような訓練があるのか解説していきます。
避難訓練
避難訓練は、建物内にいる際に災害が起こった状況を想定し、安全を確保しつつ被害の及ばない場所まで避難する訓練です。スムーズに避難経路から脱出する、地震時に机の下へ隠れるなどのプログラムは避難訓練に該当します。
避難訓練は、実際にマニュアル通りの行動を練習するまでがセットであり、防災マニュアルの作成が目的になってはいけません。避難訓練を通じた内容の周知を行わなければ、災害時における従業員のアクションは遅れてしまい、実際の被害軽減には役立たないでしょう。
仕事に追われるなか、各員に時間とリソースを割いてもらうことは勇気が必要ではあるものの、いざという場面で被害者を生まないためには不可欠な防災訓練です。
初期消火訓練
初期消火訓練は、火災が発生して間もない段階の消火訓練のことで、消火器の使用を始めとする火災発生時の対処法を学びます。
初期消火が可能となるのは「天井に燃え移るまで」といわれており、天井のほかカーテンや障子に引火した段階での消火は容易ではありません。一刻を争う場面では、消火器をスムーズに使用できるか否かが命運を分けるため、極めて重要な防災訓練の1つだといえます。
応急救護訓練
応急救護訓練では、心肺蘇生法やAEDをもちいた応急救護処置を学びます。
これらの処置は人命を救うとき重要となるものの、いずれも実生活では馴染みのない動作・操作が必要となることから、非常時にスムーズな救護活動を始めるためには訓練が欠かせません。
救助訓練
救助訓練は、てこの原理を使った負傷者の救出、ブルーシートを担架代わりにした負傷者の搬送を行う訓練です。
災害時には家具やオフィス機器、最悪の場合には家屋が崩れて倒れ掛かってきます。このような状況下では、消防隊員や救急車の到着を待っていたために、救えたはずの人命を失うという事態が起こりえるのです。
避難訓練や初期消火訓練に比べて、救助訓練は大がかりな準備を必要とするものの、負傷者の救助能力を高めるなら必須となる訓練です。
シェイクアウト訓練
シェイクアウト訓練は、市町村が主体となって行うアメリカ式の防災訓練。ホームページや自治体を通じて登録し、決められた日時に合図とともに以下の動作を行うというものです。
| シェイクアウト訓練で行われる安全確保の動作 | |
|---|---|
| 1.Drop(姿勢を低く) | その場で姿勢を低くして、飛来物の衝突を避けます |
| 2.Cover(頭と首を守る) | 落下物から身を守るため、机やカバンで頭を保護 |
| 3.Hold on(動かない) | 姿勢を低くして災害が収まるまで身を隠します |
シェイクアウト訓練のあとに、SNSで反省や感想を発信するまでがワンセットとなっており、SNSを通じて周囲の防災意識を高める役割も担っています。
自治体アカウント登録訓練
自治体アカウント登録訓練は、自治体のTwitterアカウントをフォローし、信頼性の高い団体のみ使用できる「Twitterアラート*」を登録することで、パソコンやモバイル端末からいち早く防災情報を得る体制を整える訓練です。
これにより、居住する自治体の情報収集を効率化するほか、ハッシュタグをもちいて以下のような報告をSNSに投稿する方法もあります。
| SNSを活用した状況報告 |
|---|
| 1.ハッシュタグ「#〇〇市災害」をつける。 |
| 2.場所が特定できるような写真を添付する。 |
| 3.携帯端末とTwitterアプリの位置情報を有効にする。 |
一方で、不正確な情報の拡散などが懸念されているケースもあるため、自治体ごとの規定をを確認することが良いと思います。
*追記:2022年8月現在、「Twitterアラート」は提供を終了しています。
参考:東海大学 内田 理、山田 実俊、宇津 圭祐、田島 祥、梶田 佳孝、山本 義郎「災害時のSNS利活用 現状と課題-」を抜粋・改編
発災対応型防災訓練
発災対応型防災訓練は、街中を訓練会場として行う実践的な防災訓練です。模擬災害として、周囲では火災や建物倒壊が発生し、参加者は臨機応変に負傷者の救出や消火活動を行う必要があります。
マニュアルを順番にこなす防災訓練とは異なり、より緊迫した環境下で非常時の判断力を鍛えられる防災訓練です。
災害図上訓練DIG
災害図上訓練DIGは、地図をもちいて非常時の行動を検討する防災訓練。参加者は、地図を眺めながら議論を交えて防災意識を高め、実際の被災を想定しつつ感覚を養うことが可能です。
避難所HUG
避難所HUGは、避難者の対応を疑似的に体験するゲーム形式の訓練です。配られるカードには避難者やイベントが記載されており、災害時に起こるイベントを想定したとき、どこへ避難者を配置すれば良いのか学べる内容となっています。
昨今では自治体の職員だけでなく、地域住民を主体とした避難所運営が重視されているため、運営側の目線を学べる防災関連の教材として推奨されています。
参考:
ALSOK「企業がやるべき避難訓練の流れ」
ふじのくに「DIGってなあに?」
日本防火・防災協会「避難所HUG(ハグ)」
自治体職員向けの防災訓練

自治体職員向けの防災訓練には、どのような訓練があるのか解説していきます。
災害対策本部設置防災訓練
災害対策本部設置防災訓練は、大災害が起きた場合に必要となる「災害対策本部」を立ち上げるまでの手順を確認・実践する防災訓練です。
住民や報道機関からの着信を想定した訓練、非常時の情報整理を行う訓練など、通常時とは異なる業務へ臨機応変に対応することを前提に実施されます。
参集訓練
参集訓練は、非常時に適用されるルールのもと、職員が事前に取り決めた通り参集するのか確かめるための訓練です。
災害が起こった際には、職員を中心として現場対応を行うことから、素早く適切に動くためのトレーニングとして機能します。
避難場所開設防災訓練
避難場所開設防災訓練は、災害時に住民を避難させるための「避難場所」を、いち早く開設するための防災訓練です。
防災通信機器操作訓練
防災通信機器操作訓練は、災害時に扱う防災通信機器の操作習得を目的とする訓練です。災害が発生したことを想定し、災害現場の情報共有を図るための手順と方法について確認します。
災害関連情報発信訓練
災害関連情報発信訓練は、SNSをもちいて防災情報を提供することを想定し、以下のように「Twitterアラート*」で実際に発災通知を行う訓練です。

*追記:2022年8月現在、「Twitterアラート」は提供を終了しています。
引用:首相官邸「自治体における災害時の情報発信と収集に向けて」
※2022年8月現在ページは非公開になっています。
住民協力要請訓練
住民協力要請訓練は、自治体の職員や消防隊員が現場に駆けつけられない場合に、住民に情報提供を仰ぐことで判断材料を受け取るための訓練です。
首相官邸が公表する「自治体における災害時の情報発信と収集に向けて」では、住民に以下の方法で情報提供してもらうよう示しています。
| 住民に促す情報共有の手順 |
|---|
| 1.ハッシュタグ「#〇〇市災害」をつける。 |
| 2.位置情報を有効にする。 |
| 3.状況のわかる写真を添付する。 |
引用:首相官邸「自治体における災害時の情報発信と収集に向けて」を抜粋・改編
※2022年8月現在ページは非公開になっています。
防災グループワーク訓練
防災グループワーク訓練は、図上防災訓練の1つ。複数人のグループを作り、災害条件を設定したうえで「職員が取るべき対応」について議論します。
実際に災害をイメージすることで既存の認識が改められたり、防災計画の粗を発見するきっかけになったり、マニュアルをブラッシュアップする際に役立つ訓練です。
図上シミュレーション訓練
図上シミュレーション訓練は、ロールプレイング形式で行われる臨場感を重視した図上防災訓練です。訓練は状況判断を行う「プレイヤー」と、プレイヤーに対して課題となる災害状況を与える「コントローラー」に分かれて実践します。
- 地震により電車が脱線したためレスキュー隊を出動させてほしい
- 住民からの避難方法について尋ねる電話に対応してほしい
プレイヤーは、上記のようにコントローラーから伝達される状況に対処し、次々に問題解決の判断を下していかなければなりません。
クロスロード
クロスロードは、カードゲーム形式で状況判断力を鍛える防災訓練です。カードゲームは、災害時に発生する問題を書き起こした「問題カード」をもとに進行します。
一例を挙げると、問題カードには「人数分には足りない非常食を配るか」などの、判断が難しい内容が記載されています。これに対して、参加者は熟考してYes・Noで回答し、なぜそのように考えたのか議論を行うことで状況判断力を鍛えるのです。
まとめ
例年、地震や台風は日本各地で発生しており、令和元年には「史上最大」と呼ばれる大規模な台風が甚大な被害をもたらしました。決して他人事ではなく、つぎの災害は身近な場所で起こるかも知れないと危機感を抱き、各自が防災意識を高めて訓練することが重要です。
この際、防災訓練だからといって、緊張感を持たずに取り組めば効果は半減するため、実際に被災した状況をイメージしつつトレーニングしてください。今回ご紹介した防災訓練のうち、まずは取り組めるものから実践してみましょう。
貴社のBCP(事業継続計画)対策は万全ですか?
みんなのBCPでは、企業のBCP対策に役立つ情報を紹介しております。
BCP(事業継続計画)を策定されていない場合は、以下の記事をぜひご確認ください。
■ BCPの策定を一挙解説! ■
1. 企業におけるBCP(事業継続計画)の必要性
2. BCP(事業継続計画)策定方法
3. 事業継続計画書(BCP)を1時間で作成しよう!
4. BCPとは? 便利なテンプレ集3選と、管理手法であるBCMまでを一挙解説
5. 事業継続計画策定ガイドラインを使ってみよう!自社でBCPを策定する際のポイントを解説
6. 【初動対応計画】事業継続を本気で考える人のためのキホンのキ
5,700名以上の方がダウンロードされた、BCP策定に関する資料はBCP資料ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
資料ダウンロードはこちら