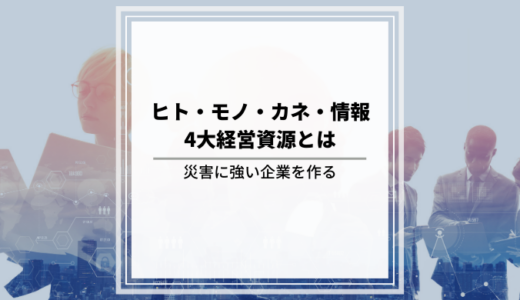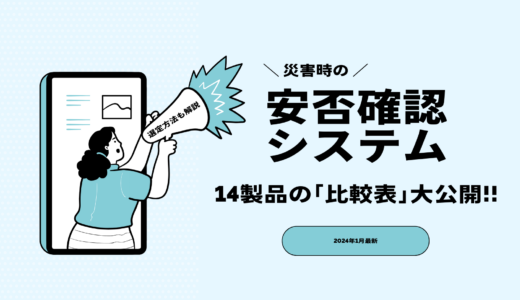尊い人命が失われる大災害。
大災害は、命だけでなく、「仕事」という、人々が生きていくために必要な生活の糧も奪います。
災害が発生した際に、企業は事業を継続し、会社を存続させるために、そして働く人は生活の糧である仕事をなくさないための計画が必要です。
だからこそ、多くの企業がBCP(事業継続計画)の策定を進めていっていますが、計画を機能させるための「訓練」を疎かになっていては、せっかくの計画も意味がありません。
防災・BCP専門のコンサルタントに依頼して訓練をするのは、コスト面で負担になりますし、自社のみで訓練を行うにしても、どんな訓練をすれば良いのかがわからない、という防災担当者・危機管理責任者の方もいらっしゃるでしょう。
今回は、万が一の際にBCPが機能するための「訓練」のあり方をお伝えします。
目次
2つの訓練方法
訓練には、大きく分けて二つの方法があります。災害が発生した際、どう行動するか、マニュアル手順などを確認する、「計画・手順確認訓練:ウォークスルー訓練」と、実際に災害が発生したシナリオの中で対応を実践する、「総合演習:フルスケールエクササイズ」の二つです。
「計画・手順確認訓練:ウォークスルー」では、BCP(事業継続計画)を机上で開き、リスクの把握と、取るべき行動、手順などを確認します。
そして、「総合演習:フルスケールエクササイズ」では、すべての担当者(可能であれば全ての従業員)が参加し、実際に災害が発生したことを想定し、対応を実践。
「ウォークスルー」を複数回繰り返した上で「総合演習」に取り掛かるのが良いでしょう。
万が一に備えたBCP訓練のあり方
それでは、実際に災害が発生したことを想定したフルスケールエクササイズの流れを確認します。
訓練開始に先立ち、どんな災害に見舞われたかを考えます。
今回は、内閣府中央防災会議が策定した首都直下地震「冬の15時、風速15m」の日に、東京湾北部を震源とする「最大震度7、マグニチュード7.3の首都直下地震」発生を想定しています。
訓練開始時刻とともに、災害発生を宣言するところから始めましょう。
ステップ1. 緊急時の連絡手段は想定済みか?

「地震の揺れが落ち着いた」という号令と共に、情報収集に取り組みましょう。
各部署ごとに担当を分け、「全従業員の安否確認」、「支社・倉庫等を含むすべての事業所の損害確認」、「在庫等の損害確認」、「事業所周辺の安全確認」を速やかに、かつ、絶え間なく実施します。
緊急時の連絡手段は確保してあるでしょうか?
大きな災害が発生すると、電話やメールでの連絡が集中するほか、通信会社などの施設に損害があった場合は、通信制限が行われます。
阪神淡路大震災、新潟県中越地震、そして東日本大震災、いずれの震災の際にも、通話の集中・基地局の損壊・停電によって、電話がつながりにくくなりました。災害時、確実につながる連絡手段を確保している必要があります。
ステップ2.バックアップ電源に頼りすぎていないか?

東日本大震災では、長引く「停電」に悩まされた企業も多かったでしょう。
PCやスマートフォン、電話、製造業では工場の設備など、現代において事業を行うには、「電気」は必要不可欠。
地震によって、発電所・送電網がダメージを受けると、停電が発生する場合があります。社内ネットワークや、重要な情報が記憶されているサーバーに無停電電源装置を備えている企業は多いでしょう。しかし、停電が長引く場合は想定できていますか?
停電が長引く場合に備え、重要な情報を抽出・バックアップを取得する訓練を行う必要があります。
企業や、入居しているビルによっては、非常用発電装置が備えられている場合もあるでしょう。
しかし、非常用発電機があっても、果たして安心といえるでしょうか?
福島第一原子力発電所の事故を思い出すと、非常用の発電機は津波によって海水を被り、起動しませんでした。同様に、大きな揺れによって非常用発電機の倒壊・故障や、給電ケーブルなどに損傷があると、当然電気は供給されません。
非常用発電機が使用不可能になり、電源を失ってしまう。もし電源喪失が「想定外」であれば、直ちに計画を見直す必要があるでしょう。
ステップ3.電気以外のインフラの確認

鉄道・道路・水道・ガスなど、電気以外のインフラのダメージも、事業にとって致命的なダメージを与えかねません。物流インフラに事業が依存している場合、代替の手段は確保してありますか?
また、水道は従業員が健康を維持するために必要不可欠なのは言うまでもありませんが、工業用水の寸断は製造業にとって大打撃を与えるでしょう。
事業を継続するために必要なエネルギーと、それを供給するインフラがダメージを受けた場合が「想定外」では致命的です。「もしもこうなってしまったら」という、神経質なまでの想定が企業を救うでしょう。
ステップ4.従業員のステータス
事業を継続するためには、従業員の存在が欠かせません。
大災害が発生した際に次々と明らかになってくる被害に、家族や恋人・友人の安否が心配になるでしょう。メンタル面を含めた従業員のステータスも把握してください。
同時に、従業員はその日に帰宅し、翌日以降再び出勤することはできるでしょうか。
内閣府中央防災会議によれば、風速15mの冬の日に「東京湾北部地震」が発生した場合、環状6号線及び環状7号線周辺の木造建築密集地帯では、大規模な火災が発生・延焼の拡大を想定しています。状況によっては、徒歩での帰宅が生命に関わる重大な危険につながるでしょう。
帰宅困難者への対策として、非常食・飲料水・簡易トイレなどの備蓄がある企業は多いと思いますが、時間を過ごすスペースのレイアウトまで想定しているでしょうか。仮眠スペース・トイレの配置次第で、従業員のフィジカル・メンタル両面の健康が損なわれる、場合によっては感染症の拡大等につながる可能性さえあります。
帰宅困難者対策も、非常食等を備蓄するだけでは足りません。スペースの確保とレイアウトまで想定してください。
「想定」を超える危機に対応できますか?
東日本大震災では、「想定外」という言葉をたくさん耳にしました。
日本観測至上最大のM8の大地震、最大遡上高40mの津波、何重にも安全策がとられているはずだった原子力発電所の大事故。なぜ、「大惨事」は起きてしまったのかを考え、導き出された答えは、「想定をはるかに超えていた」という言葉。
今日お伝えしたように、訓練とは、シナリオ通りの動きをすることだけが正解ではありません。
「もしも、この状況でこの問題が起きたらどうすれば良いか」
「訓練をしてみたところ、この部分はうまくいかなかった」
行動を見直し、計画を作り直すきっかけとなる「気付き」を発見できる機会でもあります。
それでは最後に、質問です。
大災害が起きた時、御社はその想定で事業継続できますか?
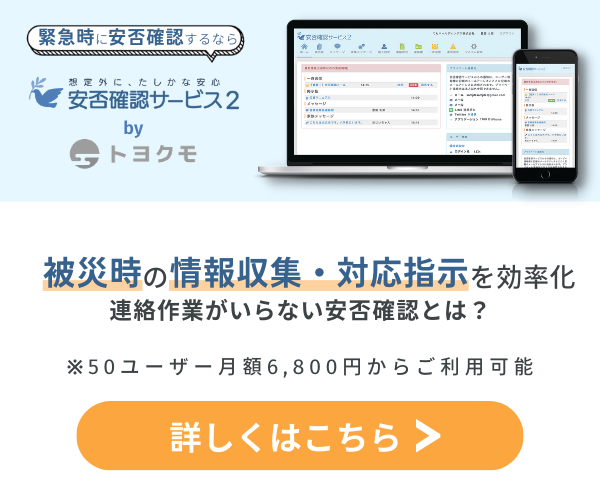
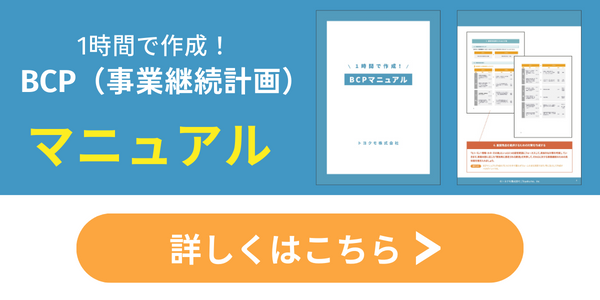
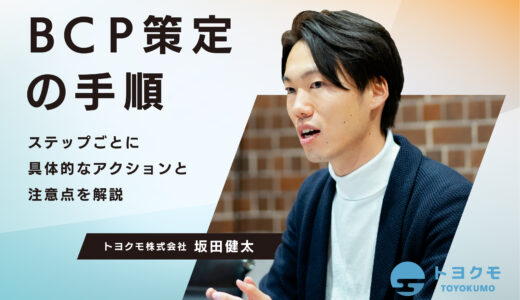
を1時間で作る!-520x300.png)