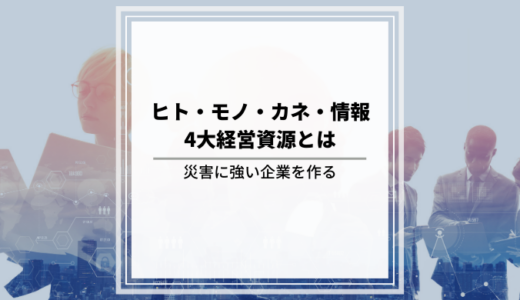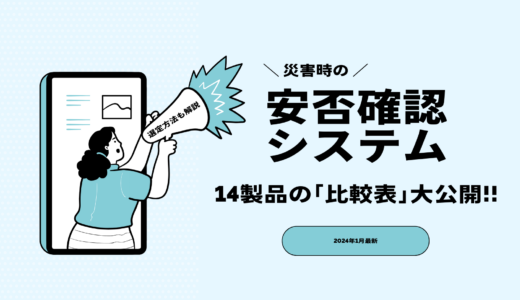「エッセンシャルワーク」あるいは「エッセンシャルワーカー」という言葉が、コロナ禍で大きな注目を集めました。
平常時・緊急事態時にかかわらず、私たちの生活を支える職種や組織、そこで働く方々をさし、医療もその一つです。ところが、厚生労働省が2019年に行った調査では、BCP策定率は、全病院で25%、災害拠点病院でも71.2%という結果になりました。
参考:厚生労働省 病院の業務継続計画(BCP)策定状況調査の結果
新型コロナウイルス(COVID-19) パンデミックだけでなく、たびたび襲う自然災害に備えるためにも、BCP策定は、どの医療施設にとっても、不可欠と思われます。
この記事では、医療施設に必要とされるBCPとその策定の手順やポイントについて解説します。


監修者:堀越 昌和(ほりこし まさかず)
福山平成大学 経営学部 教授
東北大学大学院経済学研究科博士課程後期修了 博士(経営学)。中小企業金融公庫(現.日本政策金融公庫)などを経て現職。
関西大学経済・政治研究所委嘱研究員ほか兼務。専門は、中小企業のリスクマネジメント。主に、BCPや事業承継、経営者の健康問題に関する調査研究に取り組んでいる。
著書に『中小企業の事業承継―規模の制約とその克服に向けた課題-』(文眞堂)などがある。
BCPを策定できていないなら、トヨクモの「BCP策定支援サービス(ライト版)」の活用をご検討ください!
早ければ1ヵ月でBCP策定ができるため「仕事が忙しくて時間がない」や「策定方法がわからない」といった危機管理担当者にもおすすめです。下記のページから資料をダウンロードして、ぜひご検討ください。
BCP策定支援サービス(ライト版)の資料をダウンロードする
※BCP策定支援サービス(ライト版)は株式会社大塚商会が代理店として販売しています。
目次
医療施設に必要とされるBCP(事業継続計画)とは
BCPとは、「Business Continuity Planning」の頭文字を取った言葉で、日本語では事業継続計画と訳されます。事業継続計画とは、自然災害やパンデミックなどの緊急事態が発生した際に、従業員の安全を守り、事業を存続させるための計画のことです。
病院などの医療機関にとってBCPは、緊急事態が発生しても滞りなく医療活動を継続するために必要とされています。
なお、病院におけるBCPは以下の内容を含みます。
- 医療活動を継続すること
- 医療提供現場の体制をいち早く通常水準に戻すこと
- 緊急事態下での対応力を向上させること
参考:東京都保健医療局 医療機関における事業継続計画(BCP)の策定について
医療施設のBCP(事業継続計画)の必要性
災害には、地震や津波、台風、洪水などの自然災害や大規模な交通災害、火災などさまざまな種類があります。いつどのような災害が発生するかを予測することはできないため、普段から災害が発生したときに備えて医療業務を継続できるシステムを構築しておくことが大変重要です。
平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では、マグニチュード7.2の都市直下型地震により、震度7が計測された神戸や洲本のほか、京都、大阪から九州まで、広い範囲で大きな被害が発生しました。この震災によって、震災関連死を含めた死者は6,432余名、そして負傷者は43,700余名と、かつてない甚大な被害がもたらされました。
阪神・淡路大震災が発生した当時には、前例がないほどの災害が生じたことで人員や物資の不足などさまざまな障害が起きています。この震災によって多くの患者に対応しきれなかったなどの反省すべき点があがったことを受けて、翌年には厚生省健康政策局が災害マニュアルとして「災害時における初期救急医療体制の充実強化について」を示しています。
この災害マニュアルは「被災した際の緊急体制」ですが、被災直後の一時的な対応に関するマニュアルとして、BCPとは区別されています。災害発生後の被災地では、ライフラインの遮断や人員、医薬品などの不足から医療行為に支障がでる場合が想定されます。
被災による多くの患者の治療を続けるためには、一時的な災害対応だけでなくBCPで日頃から非常時に必要なものを備えておかなければなりません。BCPで万全の備えがされていれば、治療が必要な患者をより多く受け入れられる可能性が高くなり、被災地の人的被害の拡大を抑えることにつながるでしょう。
BCP(事業継続計画)策定が義務付けられている災害拠点病院
阪神・淡路大震災のあとには、全国に災害拠点病院が設置されることも決まったため、現在では各都道府県に基幹災害拠点病院と地域災害拠点病院が指定されています。災害拠点病院とは、以下の要件を満たして都道府県に指定されている病院です。
- 24時間救急医療体制が整っている
- 災害派遣医療チームを保有している
- 災害時には通常の2倍の入院患者と5倍の外来患者に対応可能なスペースを有する
- 広域災害救急医療情報システムを整備しているなど
大災害が発生した場合には、被災地で災害拠点病院を中心に医療機関が連携して被災者を救援するための医療が行われます。災害発生時の医療機関は、災害拠点病院を中心に通常の医療業務のほかに医療救護班の派遣や多数の傷病者の受け入れなど、緊急かつ重要な業務への対応が迫られます。そのため、BCPで災害の状況への対応や、災害タイムラインに応じて変化する業務内容まで計画されていることが人的被害を抑えることにつながるといえるでしょう。
なお現状、災害拠点病院のみがBCP策定を義務付けられており、すべての病院がBCP策定を義務付けられているわけではありません。とはいえ、災害時により多くの人命を救うためにはBCPの策定は重要です。BCPを策定し、緊急事態発生時にもサービスを提供できるように準備をしておきましょう。
参考:厚生労働省 災害医療
災害による被害想定

BCPは、主に大地震などによる広域災害への対策にすることが望ましいと厚生労働省により発表されています。震災による被害が発生しても医療業務を中断させないために、また、停止した状態から速やかに医療業務を行うために、想定される災害の影響に備えるべくBCPを策定します。想定される災害の影響が事前に詳しくイメージできていれば、BCPで具体的な計画を立てられるでしょう。
大震災などの災害の際、医療機関では主に以下の問題が生じることが想定されます。
1.指揮命令系統の混乱
震災で大量の業務が発生してしまうと、人員が不足するなか、誰がどの業務を行うかの判断が難しくなります。業務量の多さに通常の指揮命令者だけでは管理、判断しきれず、担当者がそれぞれ自己判断してしまう状態になる心配もあるでしょう。そうならないよう、事前に指揮命令系統を決定しておき、重要な判断に迷う事態をなくしましょう。
2.水や電力、ガスなどのライフラインが停止
災害によりライフラインが停止すると、医療機関では備蓄された水を使用し、非常用発電機で電力を維持するなど、復旧するまでは限りあるなかで医療対応をしなければなりません。
3.院内外の電話、通信機器が使えなくなる
電力の供給が止まった場合には院内や外部と連絡を取り合うことが難しくなります。衛星電話の導入や広域災害救急医療情報システムが整備してあれば連絡が可能です。
4.施設・設備や院内の破損
物品の転倒や散乱などによる医療機器の破損や、施設の破損による危険な場所の発生などがあります。これに対しては耐震補強など、地震に対する事前対策を行いましょう。
5.傷病者の増加
被災直後には一時的に傷病者数が増加します。災害では特に緊急性の高い患者を優先する必要があるため、災害拠点病院では基本的に重傷者を中心に患者を受け入れるとされています。一般医療機関においては軽症の患者を受け入れるなど、連携した災害トリアージの実施により各医療機関の負担を分散することができます。
6.医療従事者が災害時の対応に慣れていない、人員が不足する
医療従事者全員が災害時の対応を理解していないと、実際に被災したときの動きがわからないため、適した対応をすることは難しいといえます。災害により通勤ができなくなる場合もあるため、災害対応の周知徹底や人員が不足しないよう備える必要があります。
7.医薬品の不足
病院で備蓄されている医薬品の数には限りがあります。不足することがないよう、他院との連携を取るなど綿密な対策を立てておきましょう。
医療施設のBCP策定の手順とポイント

BCP策定時には、まず医療機関の方針を決定し、院内で権限のある院長などが責任者となり病院内の各部門長などがそれぞれ検討組織に参加することが重要とされています。できるだけ幅広い部門からメンバーを集めることにより、各部門との連携が取りやすくなるというメリットが得られるでしょう。
次に、指揮命令系統や人員、資器材など、災害時に必要なものがどれだけ揃っているかなど病院の現状を把握します。そして想定される災害が発生したときにどれくらい耐えられるのか分析します。時間が経つにつれ、状況がどう変化していくかを予測し、時系列で必要な対応をまとめる点もポイントといえます。
BCPは一度策定すれば終わりというものではなく、常に変化していく病院や環境に対応するために改善を続ける必要があります。PDCAサイクルの流れを取り入れ、「方針の決定」「BCPの策定」「教育・訓練の実施」「実践」「実践・訓練の検証」「見直し」を繰り返すことで、いつでも災害に対応できるBCPを備えることができるでしょう。
BCPを策定の手順とポイントを詳しく解説します。
1.業務・指揮の優先順位付け
業務と指揮の優先順位を決めます。規模が大きい医療機関の場合は、部門ごとに指揮を担当する人を決めましょう。規模が小さい場合はBCPの責任者が指揮をとるとよいでしょう。
ただし、緊急事態はいつ起こるか分からないため、指揮をとる人が不在の場合に誰の指示が優先されるかも決めておく必要があります。
また、従業員の数が十分でないときに、優先して復旧する業務を決めておきましょう。なぜなら、緊急事態が発生すると、従業員が出勤できなくなる可能性があるからです。医療提供に必須の業務を把握して、最優先で復旧させていきましょう。
2.現状の把握
現状を把握します。現体制の改善点を洗い出したり、停電や断水などが発生した際の対応方法の確認、人員の確保手段の確認を行いしましょう。
緊急事態時の病院では人員不足・停電・断水などが起こる可能性があります。対応方法を決めるには、現状の把握が不可欠です。もし、停電や断水への対応が十分ではない場合は予備電力や設備の追加など、何かしらの対策が必要となるでしょう。
また、設備や人員数をもとに緊急事態時に対応可能な患者数を設定しておくことも大切です。とくに、自然災害の発生や感染症の蔓延時には、通常より遥かに多くの患者が来院することが予想されます。患者数によってはすべて対応できない恐れもあるため、あらかじめ対応可能な患者数を想定しておきましょう。
3.医療需要への対応力の強化
緊急事態時には、平常時よりも多くの医療需要が発生します。つまり、平常時以上の医療提供能力を確保しなくてはなりません。
しかし、緊急事態が発生した際は従業員が出勤できない可能性も十分にあります。加えて、医療品や医療機材が不足する事態も想定されます。このような状況にならないための対策が必要です。
平常時から医療品の在庫を多めに確保しておくことはもちろん、お互いに助け合えるように近隣の病院や薬局と連携を図っておきましょう。
4.インフラ対策
インフラ対策も不可欠です。病院におけるインフラ対策としては建物の耐震性、通信手段の確保、電力の確保などが挙げられます。
たとえば、地震が発生したときに病院が倒壊しては医療提供ができません。入院患者の命も危うくなるでしょう。地震に備えて建物自体の耐震性を高めたり、倒れそうなものは固定したりするなどの対策が必要です。
また、自然災害が発生すると通信障害が発生するリスクがあります。通信障害やサイバー攻撃に備えて、バックアップデータを確保することも大切です。
さらに、電力の確保も欠かせません。自然災害発生時は停電や断水のリスクがあります。電力の供給が止まらないように、電力の確保も必ず行いましょう。
5.従業員の緊急招集対応
従業員の緊急招集対応もBCP対策に含まれます。医療提供を行うためには従業員が必要不可欠です。
緊急事態により、本来出勤予定だった従業員が出勤できなくなるかもしれません。このようなリスクを想定し、緊急時の出勤判断を各自で行うためのルールを決めておきましょう。
6.帰宅困難者の対応
緊急事態発生時、交通機関の運行停止などによって、外来患者や来院者が施設内に滞在しなければならないかもしれません。
このような状況でも従業員や帰宅困難者がパニックにならないよう、あらかじめ滞在スペースを確保しておきましょう。
7.被害の想定
被害を想定しておけば、対応方法が明確になります。過去の事例をもとに、被害状況を想定しておきましょう。
ただし、被害状況は時間経過とともに変化することに注意しなければなりません。たとえば、停止していた交通インフラが復旧すれば、対応できる医療機関の数が増えたり従業員が出勤できるようになります。被害を想定する際は、時間経過ごとの状況も考慮しましょ
8.インフラ復旧の予測
インフラの復旧にどの程度時間がかかるかの見込みを立てておきましょう。
緊急事態発生時には、インフラが停止する可能性があります。過去に起きた自然災害のデータをもとに、インフラが復旧するまでにかかる時間を予測し、医療提供を維持できる設備を設置しましょう。
医療施設のBCP対策には『安否確認サービス2』を活用しよう
災害時にはトヨクモが提供している『安否確認サービス2』の活用がおすすめです。
安否確認サービス2は、2022年9月時点で導入社数が3,000社以上を誇る安否確認システムです。気象庁の情報と連動して、従業員の安否確認メールを自動で送信します。複数のメールアドレスや専用アプリ、LINEにも通知できるため、安否確認通知の未達を防げるでしょう。
とくに魅力的なポイントを以下に紹介します。
- BCPに必須の機能が搭載されている
- 毎年一斉訓練を実施している
- サービスの品質保証制度を導入している
- 管理と運用が手軽にできる
BCPに必須の機能が搭載されている
トヨクモの安否確認サービス2には、BCPに必須の機能が搭載されています。
災害発生時は従業員の安否確認だけではなく、一部の従業員と今後についての議論や、あらゆる情報の共有をしなければいけません。安否確認サービス2には以下の3つの機能が搭載されており、議論や情報共有を簡単・迅速に行えます。そのため、災害時の事業継続や医療への参加もスムーズにできます。
| 概要 | 用例 | |
|---|---|---|
| 掲示板 | すべてのユーザーが書き込めるため、情報共有に活かせる | ・被災状況の伝達 ・災害時のマニュアル掲載 |
| メッセージ | 宛先を指定したユーザーのみが閲覧・書き込みができる | ・一部の従業員との議論 ・部署単位での情報共有 |
| 一斉送信メール | 情報を一斉送信できる | ・被害状況の回答 ・災害時の対応 |
これらの機能は通常時も活用できるため、日頃から操作して使い慣れておけば非常時の混乱を避けられるでしょう。
毎年一斉訓練を実施している
安否確認サービス2では、毎年防災の日である9月1日に全国一斉訓練を実施しています。一斉訓練に関する情報は実施日と時間帯のみしか知らされないため、実際の災害時と同じような状況下で通知を受け取ることになります。そのため、システムが安定して稼働しているかどうかをチェックできるのがポイントです。
また、訓練終了後には回答情報を集計し、そのレポートを各組織に送付しています。社内の回答率や時間推移、平均回答時間などをチェックでき、自社の防災意識を高めるきっかけとなるでしょう。
サービスの品質保証制度を導入している
安否確認サービス2は、サービス品質保証基準を設定しています。サービス品質保証とは、サービス提供者が提供しているサービスの品質について一定基準の水準を保証していることです。この水準を下回った場合は、サービスの利用者に対して返金や適切な措置が行われます。
安否確認サービス2ではプレミアムプラン以上から適用され、維持できなかった場合は利用料金の一部を返金すると定めています。しかし、安否確認サービス2は現在まで保証基準を下回ったことがないため、災害時でも安心して利用できるでしょう。
管理と運用が手軽にできる
安否確認サービス2では、管理と運用をスムーズに行えるのも魅力の一つです。たとえば、Google WorkspaceやMicrosoft Entra IDといった外部システムを活用すると、1クリックでユーザーや部署の情報を登録できます。
また、安否確認サービス2では定期的に自動でメールを送信しており、登録された連絡先が有効であるかどうかもチェックできます。そのため、緊急時にメールが届かないといったリスクの軽減につながるでしょう。無効なメールアドレスを配信対象から除外できるため、メール全体の信頼性が向上し、迷惑メールと判断されにくくなるのもポイントです。
医療施設におけるBCPの必要性を理解しよう!
BCP(事業継続計画)を策定して、 自然災害や感染症などの非常事態に備え、あらかじめ行動を想定しておくことで、冷静な判断が可能となり、患者の命を守るだけでなく、医療従事者の安全確保や医療体制の迅速な復旧にも繋げることができます。2017年度に災害拠点病院ではBCP策定が義務化されているので、今後の対応方法を検討すべきでしょう。
BCPを策定できていないなら、トヨクモの「BCP策定支援サービス(ライト版)」の活用をご検討ください!
早ければ1ヵ月でBCP策定ができるため「仕事が忙しくて時間がない」や「策定方法がわからない」といった危機管理担当者にもおすすめです。下記のページから資料をダウンロードして、ぜひご検討ください。
BCP策定支援サービス(ライト版)の資料をダウンロードする
※BCP策定支援サービス(ライト版)は株式会社大塚商会が代理店として販売しています。


監修者:堀越 昌和(ほりこし まさかず)
福山平成大学 経営学部 教授
東北大学大学院経済学研究科博士課程後期修了 博士(経営学)。中小企業金融公庫(現.日本政策金融公庫)などを経て現職。
関西大学経済・政治研究所委嘱研究員ほか兼務。専門は、中小企業のリスクマネジメント。主に、BCPや事業承継、経営者の健康問題に関する調査研究に取り組んでいる。
著書に『中小企業の事業承継―規模の制約とその克服に向けた課題-』(文眞堂)などがある。
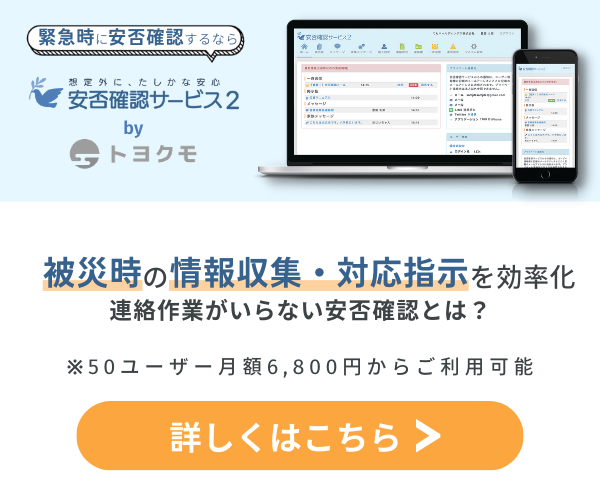
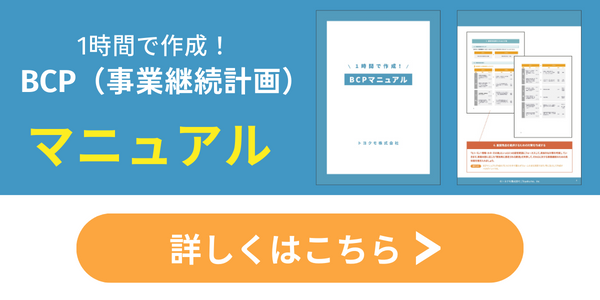
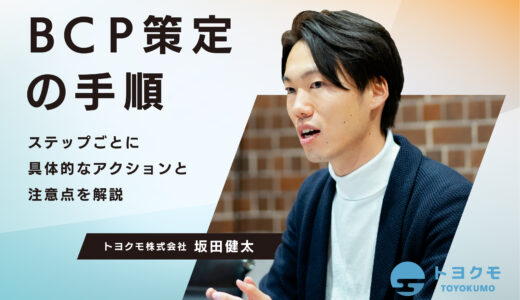
を1時間で作る!-520x300.png)